【ゆうらリズム】ひきこもる気持ちを、わかってほしい
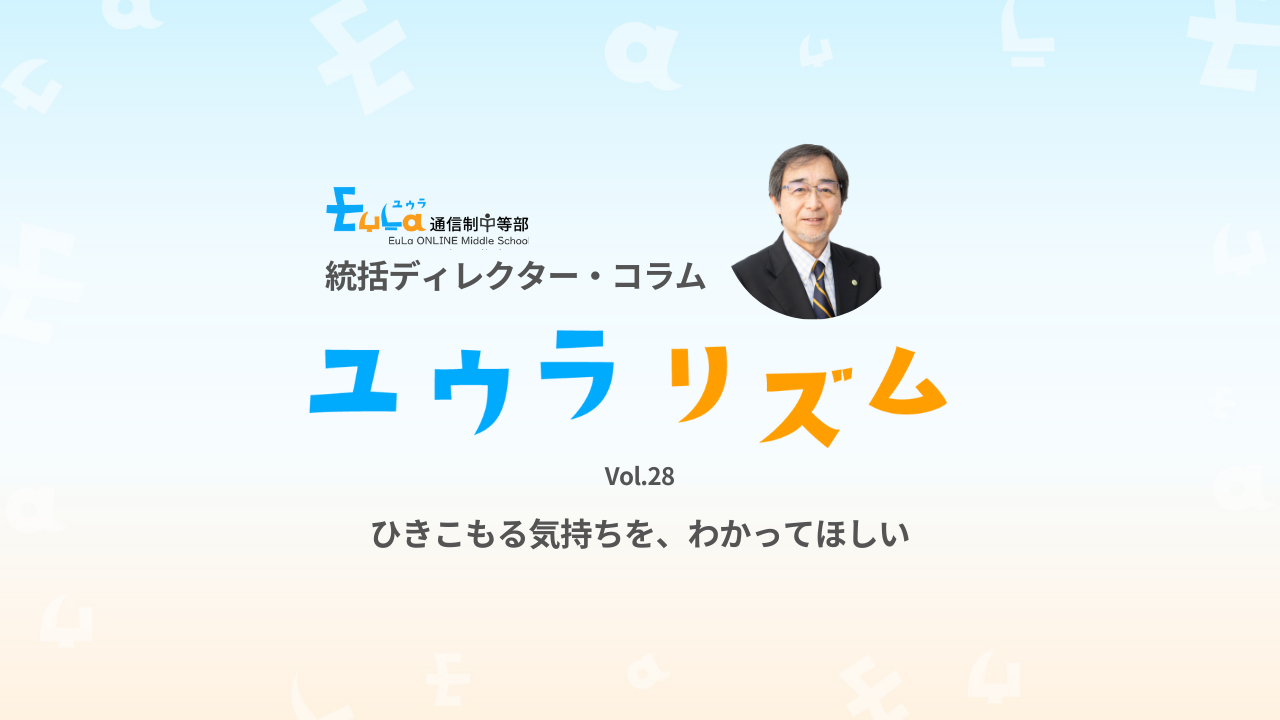
私には、中学時代に2ヶ月学校に行けなかった時期がある。
9月と10月。担任との相性の悪さ、体調の不調が重なって、心がすり切れてしまった。
「休むしかない」と思うほど、私は困憊していたのだ。
「まあ、いいか」と切り替える術も知らない年頃だった。
消極さと、どこか強がるような積極さが混じり合う、複雑な気持ちだけが胸の中に残っていた。
今振り返ると、消極的な気持ちと、どこかで抵抗している積極的な気持ちとが、ないまぜになっていたように思う。
もしあの頃の自分を大人の私が分析するなら、「ドロップアウト」なのか「スピンアウト」なのか、あるいは「スピンオフ」なのか——そんな言葉で説明しようとするかもしれない。
教室は窮屈な空間だった。
担任は“暴君”のように思想・信条を押しつけてくる。
その暴力的な言葉の圧に耐えるには、私は少しだけ繊細すぎた。
上手に聞き流すことも、鈍感にふるまうことも、うまくできなかった。
「この中で校長に告げ口したやつがいる」
そう言って、クラス全員の前で担任が私を一瞥した日の空気はいまでも覚えている。
高校時代も、学校よりも私を育ててくれたのは、ソルジェニーツィンや大江健三郎、司馬遼太郎、倉橋由美子らの小説世界だった。
河原に寝転び、本の中で呼吸をしていた。
私にとって、もっとも“学べる場所”は教室ではなく、彼らの言葉が紡ぐ空間だったのだ。
大人になった今でも、ときどき心がひきこもる。
たとえば——
●いくら頑張っても、誰にも認めてもらえないと感じたとき
●信頼していた人から圧をかけられたとき
●まわりの人が話すばかりで、私の声を聞こうとしないとき
●うまく話せない私を遮って、頭ごなしのアドバイスが飛んできたとき
●自分の成功談に酔いしれ、こちらの気持ちを想像しようともしない人に出会ったとき
私はただ、「嬉しいよ」「頑張ってるね」「つらかったね」と、静かに耳を傾けてほしいだけなのに、問題解決を急ぎ、私の心の中に踏み込んでくる人に出会うと、心がキシキシと悲鳴を上げる。
そんな経験を繰り返してきたからこそ、ひきこもりたい気持ちは“異常”ではなく、むしろ自然な反応だと今はわかる。
わかってくれない大人の横暴さの前では、いくつになっても心が怯む。
たとえ80歳になっても、自己愛をふりかざす大人に対しては、きっと辟易し続けるだろう。
過去を懐かしんでは今を揶揄し、皮肉や嘲笑を織り交ぜて語る人に出会ったなら、私はそっと席を立つ。
だからこそ私は、
教室で居心地の悪さを抱える生徒が気になって仕方がなく、結果として学校を四つもつくってしまったのだと思う。
そしてまた一つ、日本初の通信制中学校を目指して、EuLa通信制中等部を開校した。
どれも“普通”とは言えない学校になったのは、未来に向かって歩こうとする子どもたちに居場所をつくりたかったからだ。
私は、過去を振り返り続ける人よりも、未来を信じ、未来に生きようとする人とともに歩きたい。
ひきこもった経験のある私だから、心が疲れたとき、立ち止まることの大切さも知っている。
そしてまた歩き出す力を、誰もが必ず持っていることも知っている。
日野 公三
EuLa通信制中等部 統括ディレクター
明蓬館高等学校 理事長
アットマーク国際高等学校 理事長
東京インターハイスクール特別顧問(創立者)


