【ゆうらリズム】競争から共創へ ~インクルーシブ教育とは
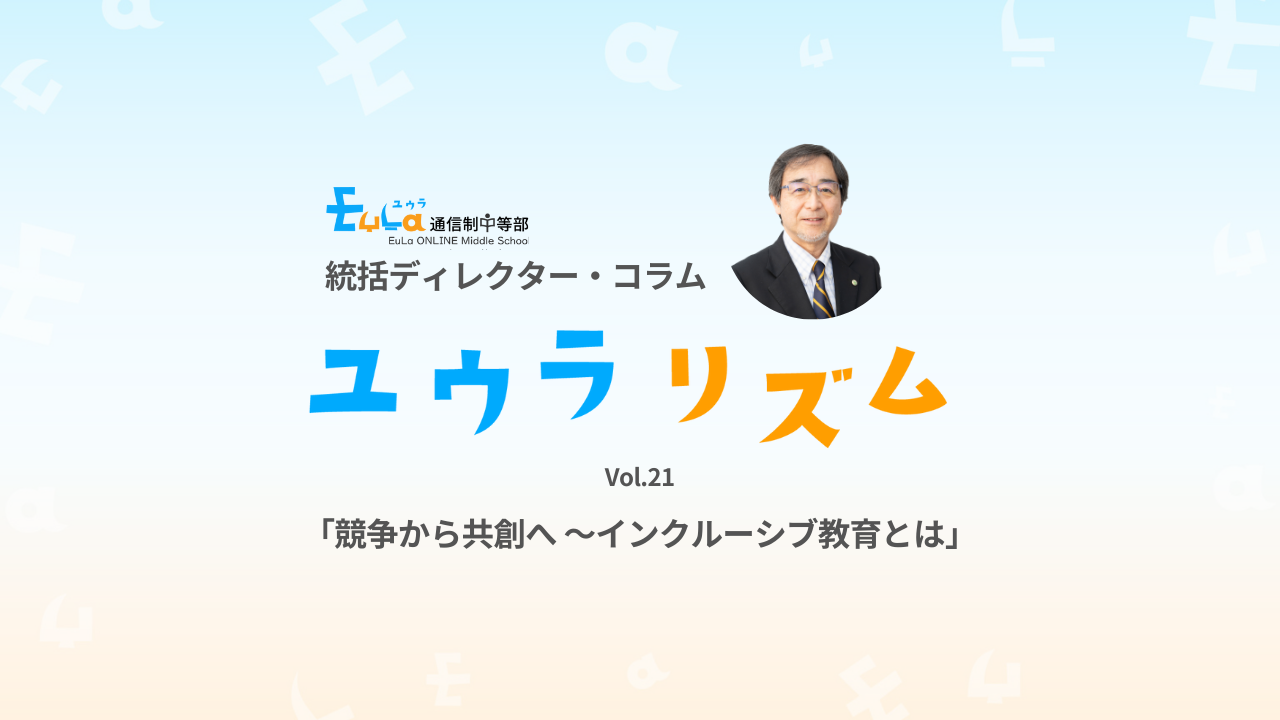
インクルーシブ教育を、どういうレイヤーで定義するのか。
一般的には、インクルーシブ教育には、障害を持つ子供と障害を持たない子供が共に学ぶことで、障害を持つ人がその能力を最大限に発揮し、自由な社会に効果的に参加できるようにするという目的があります。
そのためには、設備・施設・教育課程・支える教職員体制、スキル・ワークフローの整備、校長をはじめとするマネジメントのあり方の見直し等々、難問が山積しています。
その現実を知る、校長、私立の理事長らは、私にこう言いました。
❝明蓬館高校の特別支援教育は凄いですね。そこまでおやりになっているのですね。
わが校はインクルーシブ教育なので、障害のある生徒もない生徒も分け隔てせずに一緒に教育しています❞
それは、少し理解が違うようです。
インクルーシブ教育を、多職種連携による科学的で専門的な特別支援教育をやらない、都合の良い言い訳に用いるのは違います。
思考を止めてしまうのは危険です。
視点を変えてみます。
教室に集う児童生徒みんなを成功者にして、教室全体で高い達成感を手に入れられるようにゲームのルールを見直し、生徒同士も話し合い、だれもがチームの勝利に貢献できるようにする。
一握りの勝者を作り出すために多くの敗者を作り出すことのないようにする。
みんながゲームに参加できるようにする。
競争の教室から共創の教室へと進化させる。
みんなを勝者にし、笑顔にする。
笑顔でなくてもその場にいたいと思えるようにする。
私見ですが、教育の現場におけるインクルーシブ(統合もしくは包括)の考え方の基本にあるものは、どうやらそのあたりにあるのではないかと考えてきました。
教室も、社会もつまるところ、同じです。
子どもたちがこの先、生きていく社会を想像し、そのための予行演習の場としての教室を創る。
競争環境の教室で多くの時間を過ごしてきた人は、社会でも競争環境を求めがちです。
多様な人と異見、利害を乗り越えて共通項を見出し、共生していく社会を思い浮かべるのであれば、そのための教室の在り方は決まっていきます。
私には障害はない、私には無縁だと思っても、どんな人にもいずれ何らかのスペシャルニーズが発生します。
どんな人も、障害から無縁ではありえないのです。
合理的配慮が必要な当事者になります。
学校教育の役割はとても大きなものがありますね。
そんな明蓬館高等学校のインクルーシブ教育の考え方と実現方法は、EuLa通信制中等部にも引き継がれています。
日野 公三 EuLa通信制中等部 統括ディレクター
明蓬館高等学校 理事長


