【ゆうらリズム】新しい学校が重視されなければならない時代
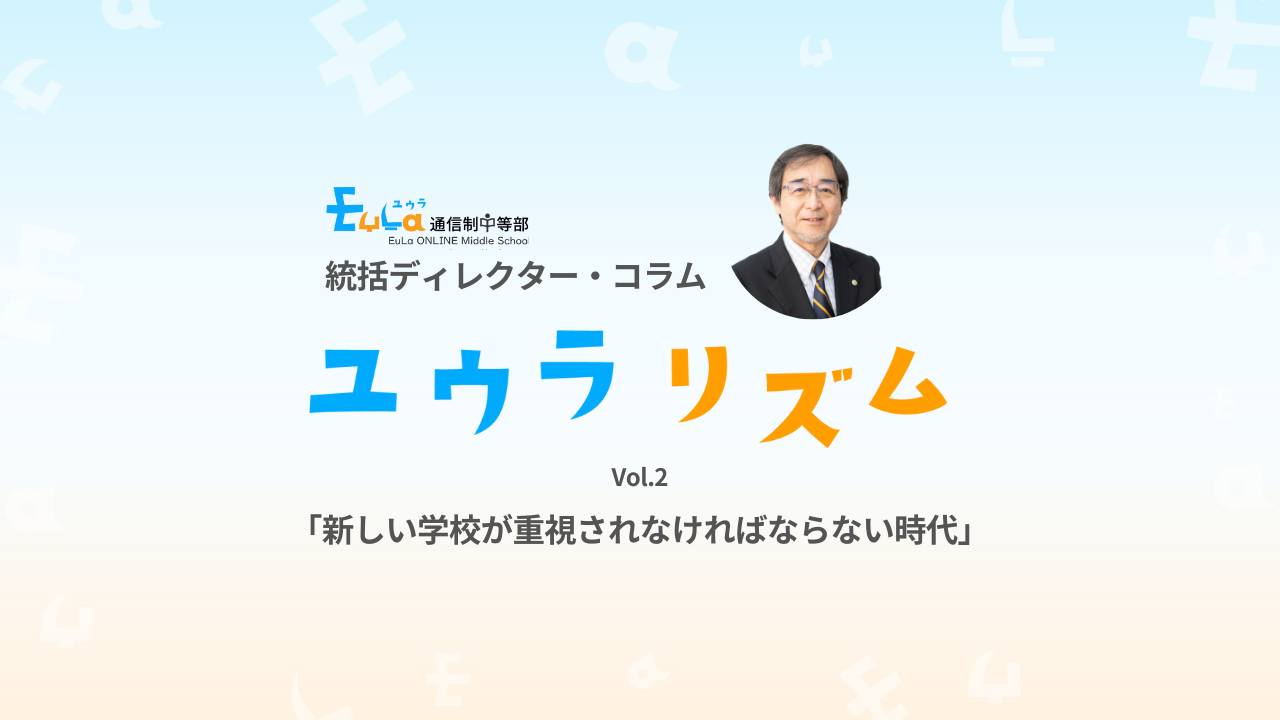
幕末の私塾と教育の多様性
幕末には、学者や教育者が開設した私塾が全国に約1500もあったといわれています。
藩校・郷校と並び、私塾や寺子屋といった民間教育機関が普及し、単なる教養の習得だけでなく、精神修練を重視する教育が行われていました。
個人の習熟度や地域性に合わせて、在学年数さえも自由だったのです。
企業や民間による学校設立の歴史
近年、特区法に基づき、特定の市町村に限り株式会社立学校が認められましたが、近代以降の日本では、企業や企業人によって設立された学校は珍しくありません。
明治維新後、日本は欧米列強に追いつくため急速な学制改革を進めました。
しかし、国庫負担だけでは学校を増やすことが難しく、私立学校の許認可や規制は比較的緩やかに運用されていました。
その結果、私立学校の設置は自由度が高く、多くの学校が誕生しました。
教育政策と私学への圧力
西南戦争や自由民権運動を経て、政府内の権力闘争が激化し、教育政策にも政治的な圧力が加わりました。
福澤諭吉の『学問のすすめ』は空前のベストセラーとなりましたが、政府が教育に深く関与することの危険性を説いたため、明治政府によって警戒され、禁書とされることもありました。
また、私学への規制は一進一退を繰り返しました。
慶應義塾のように官公立教員や学校長を輩出していた私学も圧迫され、1884年には、文部省が「師範学校出身者以外は官公立学校の学校長になれない」とする方針を打ち出しました。
さらに、私学の学生は官公立学校の学生と同等の徴兵免除を受けられなくなるなど、私学冷遇政策が次第に強まっていきました。
大正期に訪れた教育の自由化
しかし、大正時代になると、教育界に規制緩和の波が押し寄せました。
アメリカの教育思想家ジョン・デューイを代表とする自由主義型の教育思想が流入し、「家庭科」「社会科」といった実践的な教科が誕生しました。
日本でも、現場の教師たちによる教育改造運動が展開され、子供たちを学習の主体とする「大正自由教育運動」が盛り上がりを見せました。
「自由」や「文化」という言葉が流行し、成蹊小学校、明星学園、玉川学園、和光学園、文化学院、自由学園といった新たな私学が注目されるようになりました。
私学の経営と自立の精神
当時の私学の多くは、公的な補助金に頼るのではなく、卒業生や篤志家の寄付、あるいは学校独自の産業活動によって経営を維持していました。
学校自身が自立しなければ、生徒・学生の自立を促すことはできないと考える創立者が多かったのです。
このように、時代の変革期には、新たな教育運動が民間教育、特に私学から始まることが多かったのです。
未来の教育を創造する時代へ
これからの時代、児童・生徒・学生を「未来からやってきた留学生」と捉え、その主体性を尊重する私学が再び教育の先頭に立つべきではないでしょうか。
そろそろ、新しい学校が群れとなって、教育界にうねりを起こす時代が訪れるべきです。
それは昭和・平成の影を振り払った、一世紀ぶりの「未来型の学校」です。
それは「児童・生徒・学生ファースト」の学校なのです。
TEDxFukuoka2023
答えはすべて生徒の中にある 日野公三


